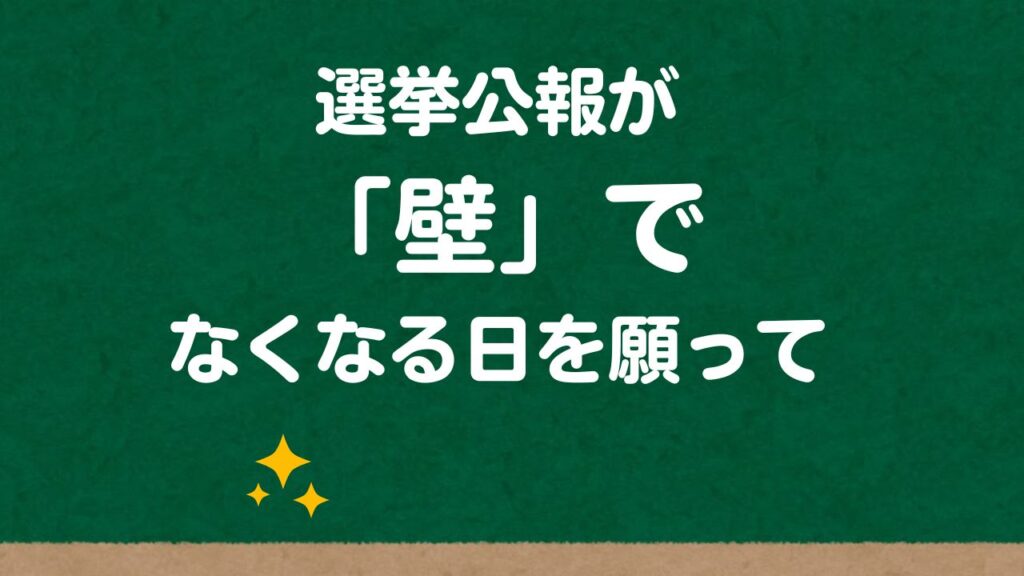
こんにちは。アスカネットの飛鳥です。私は視覚障害者として、日々スクリーンリーダーを使い、PCやスマホで情報を得ながら生活をしています。
2025年7月20日、参議院選挙の投開票が行われました。私も、一人の有権者として、誰に未来を託すかを考え、投票所に足を運びました。
その判断のために、最も重要な情報源となるのが「選挙公報」です。近年は多くの自治体でPDF版がWebサイトに公開され、「音声読み上げ対応」も進んでいます。しかし、そのPDFを開いた時、私にとってそれは「情報」ではなく、解読が必要な「パズル」に変わってしまうことがあるのです。
「読める」と「伝わる」のあいだにある、深い溝
「音声読み上げ対応」と書かれた選挙公報のPDF。しかし、スクリーンリーダーで読み上げを開始すると、多くの場合、私はまず「これが正しく読めるかどうか」を確かめる作業から始めなければなりません。
- 文章がバラバラに読み上げられる
ポスターのようにレイアウトされた公報では、縦書きと横書きが入り混じっていることも多く、スクリーンリーダーは見た目の通りには読んでくれません。例えば、候補者の「経歴」を読み上げたかと思えば、次は「公約」の3番目にジャンプし、また「趣味」の部分に戻ってくる、というように文章の順番が意味不明なことが多く、候補者が何を言いたいのかを理解するのが非常に困難です。 - 画像が「イメージ」とだけ発声される
候補者の顔写真や、政策を説明する重要なグラフが、ただ「イメージ」とだけ読み上げられる。そこに何があるのか、全く情報が伝わってきません。 - 見出しがなく、情報の構造が分からない
どこが名前で、どこが公約なのか。見出し構造がなければ、ただの長い文章の塊です。目的の情報を探すには、全文を聞き通すしかありません。
この「読みにくさ」を乗り越え、内容を把握するために、私たちは多大な労力を強いられています。この負担は、本当に私たちが乗り越えなければならないものなのでしょうか。
なぜアクセシブルではないのか? Web制作者と視覚障害者の視点から
Web制作者として、そして視覚障害者としての私の視点から見ると、これらの問題の多くは、悪意ではなく「作り方の知識不足」と「当事者による検証の欠如」から生じています。
善意で「音声読み上げ対応」というチェック項目をクリアしたとしても、実際にスクリーンリーダーでどう聞こえるかを確認しなければ、それは真の「対応」とは言えません。
現状は、情報を提供する側が「対応した」という事実を作るだけで満足してしまい、情報を受け取る側の私たちが、その不備を我慢と努力で補っている、というアンバランスな構造になっているのです。
誰もが情報にアクセスできる選挙の形を考えてみる
では、どうすればこの状況は改善するのでしょうか。
Web制作者として、そして視覚障害者として、以下の方法を提案します。
提案1:当事者を巻き込んだ「正しいPDF」の作成プロセスを
まず、PDFで提供するならば、その作り方の指針を見直すべきです。そして何より、完成品を公開する前に、実際にスクリーンリーダーを使っている視覚障害者や、アクセシビリティの専門家がチェックする仕組みが不可欠です。当事者が関わることで、「読める」と「伝わる」の溝は確実に埋まります。
提案2:PDFからの脱却。HTMLとテキストこそが最善の策
これが、私が最も強く推奨する解決策です。
そもそも、なぜPDFにこだわる必要があるのでしょうか。候補者の情報を、ウェブページ(HTML)そのものや、単純なテキストファイル(.txt)で公開すれば、問題の多くは解決します。
適切に見出しが設定されたHTMLページであれば、スクリーンリーダーの利用者は、自分の知りたい情報(経歴、公約など)に一瞬でジャンプでき、その体験はPDFとは比べ物になりません。
【未来への提案】候補者向け「アクセシブル公報作成システム」
もし、各候補者がHTMLなどに対応するのが難しいのであれば、選挙管理委員会が「アクセシブル公報作成システム」のようなものを用意するのはどうでしょうか。
これは、候補者が必要な項目(氏名、経歴、公約など)をフォームに入力していくだけで、自動的にアクセシビリティが担保されたWebページが生成される仕組みです。このようなシステムがあれば、候補者のITスキルに左右されず、すべての情報が公平に、かつアクセシブルに提供されます。(もし需要があれば、私自身がそうしたシステムの開発に協力したいとさえ思っています。)
まとめ:情報へのアクセスは、民主主義の土台です
選挙における一票の価値は、誰にとっても平等です。
しかし、その一票を投じるための判断材料である「情報」に、アクセスしやすさの差があって良いはずがありません。
「音声読み上げ対応」という言葉だけで満足せず、それが本当に「伝わる」形になっているか。
その検証と改善のプロセスに、ぜひ私たちを加えてください。
誰もが等しく情報を得られ、自らの意思で未来を選択できる。
